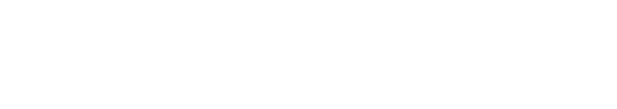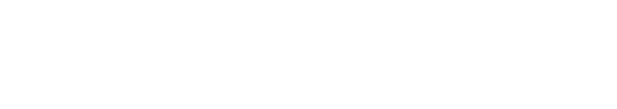ぽかぽか陽気に誘われて、お出かけが楽しくなる季節になりました。
こんにちは。ほと子です。
お散歩や旅行でお寺を訪れたとき、「お寺にはいろんな建物があるけど、それぞれ何のためにあるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、お寺の建物には、一つひとつに役割があるんです。今回は、そんなお寺の建物について、楽しく分かりやすくご紹介します!
そもそも、お寺って何のためにあるの?

「お寺って、お葬式や法事をするところでしょ?」と思っている方もいるかもしれませんね。しかし、もともとお寺は修行の場でした。仏教の教えを学び、心を整えるための場所だったんです。
仏教の開祖・お釈迦さまが弟子たちと共に各地を旅しながら修行していました。やがて仏教の教えを求める人が増え、お釈迦さまは信者から寄進された土地に修行の拠点を設けるようになりました。その拠点が、お寺のルーツです。
特にインドでは、雨季のあいだ、虫や草花を踏まないように外出を控える「安居(あんご)」という修行がおこなわれていました。期間中、洞窟などで静かに修行をするなかで、次第にお寺という定住の場が生まれていきました。
お寺の基本的な建物は7つ!

お寺には「七堂伽藍(しちどうがらん)」と呼ばれる主要な7つの建物があります。すべてのお寺に七堂伽藍があるわけではありませんが、歴史ある大きな寺院の多くではこの形式が取り入れられています。ここでは、7つの建物についてひとつずつ詳しく見ていきましょう!
金堂(こんどう)
お寺のメインスポット! お寺によっては「本堂(ほんどう)」と呼ばれることもあります。 奈良県にある東大寺の大仏殿も、正式には「金堂」にあたります。金堂の内部にはきらびやかな装飾が施されており、とても神聖な雰囲気です。ご本尊が安置されていることもあり、多くの人が手を合わせに訪れる、お寺の中心的な場所となっています。
講堂(こうどう)
お坊さんたちが仏教の教えを学ぶために使っていた勉強部屋、それが「講堂」です。昔はここで経典(きょうてん)の講義がおこなわれ、修行僧たちが熱心に学んでいました。現在ではあまり見かけなくなりましたが、滋賀県の比叡山延暦寺にある「大講堂」のように、歴史あるお寺には講堂が残されています。お寺はただお参りする場所というだけでなく、仏教の知識を深める学びの場でもあったんですね!
塔(とう)
塔は、お寺のシンボル的存在で、観光スポットとしても人気です。もともとはお釈迦さまの遺骨を納めるための建物でした。
塔の形にはさまざまな種類があり、五重塔や三重塔のほか、インドのストゥーパに近い半球形のタイプもあります。仏教が日本に伝来して以降、宗派ごとに独自の理念が反映され、塔のデザインも異なる形へと発展しました。ちなみに奈良県の法隆寺の五重塔は、日本最古の木造建築として有名です。
鐘楼(しょうろう)
お寺で「ゴーン……」と響く鐘の音を、聞いたことがありますか? あの厳かな音を奏でるのは「梵鐘(ぼんしょう)」で、梵鐘を吊っているのが鐘楼と呼ばれる建物です。梵鐘には、時刻を知らせる、大切な行事の合図を送るなどの役目があり、昔からお寺に欠かせない存在です。特に有名なのが、大みそかの除夜の鐘。108回鳴らされる鐘の音には、「悩みや迷いをすっきりさせて、新しい気持ちで新年を迎えよう」という願いが込められています。
経蔵(きょうぞう)
経蔵は、仏教の大切な書物を保管するための建物です。昔は紙の本がとても貴重だったので、それらを守るために専用の建物が作られました。お寺の「図書館」といったところでしょうか。
現在では多くの経典がデジタル化され、経蔵のあるお寺は少なくなりましたが、奈良の東大寺では今もその姿を残しています。
食堂(じきどう)
「食堂」という漢字を見ると、学校や会社の食堂を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。お寺の食堂は、お坊さんたちが食事をするための場所です。ここでは、お肉や魚を使わない「精進料理」が提供されます。
最近は、一般の人でも精進料理を体験できるお寺が増えていて、京都の妙心寺などで気軽に楽しめます。
僧房(そうぼう)
お坊さんが寝泊まりする場所は「僧房」と呼ばれ、時には「僧坊」とも書かれますが、どちらも同じ意味です。昔は修行の場でもありましたが、今では一般の人が泊まれる「宿坊(しゅくぼう)」として利用されることも増えています。
たとえば、和歌山県の高野山にはたくさんの宿坊があり、実際にお坊さんの生活を体験することができます。精進料理を味わったり、朝のお勤めに参加したりと、特別な時間が過ごせるので、外国人観光客にも人気! 静かな空間で心を落ち着けたい人には、ぴったりの宿泊体験ができそうですね。
まとめ

昔は「七堂伽藍」がそろったお寺が数多く存在していました。しかし、時代の変化とともにお寺の形も変わり、現在では7つの建物すべてがそろっているお寺は少なくなっています。
現在のお寺は写経や座禅、寺ヨガを体験したり、宿坊に泊まって精進料理を味わったりと、いろんな楽しみ方ができる場所になり、身近に感じられるようになりました。心を整えたいとき、ちょっとリフレッシュしたいときにもいいですよね。
次にお寺を訪れたときは、「この建物って何のためにあるんだろう?」と、意識を向けてみてください。お寺の新しい一面に出会えて、いつものお参りがもっと楽しくなるかもしれませんよ!
過去に花手水が綺麗なおすすめの寺院も紹介しておりますので、訪問するお寺を選ぶ際の参考にもぜひ。
【参照サイト】
https://discoverjapan-web.com/article/1964
https://www.narakanko.net/knowledge/structures.html
https://usukimeguri.com/blog/knowledge12/
https://www.homemate-research-religious-building.com/useful/glossary/religious-building/2030401/
https://www.shukubo.net/contents/reserve/
https://www.todaiji.or.jp/information/daibutsuden/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E5%A1%94
高野山


東大寺
五重塔(仁和寺)

ほと子’s choice

トラベルポーチ セット おしゃれ 旅行 衣類収納 出張 整理 便利グッズ
¥1,930
![]()
【食洗機対応】象印マホービン 水筒 400ml お手入れカンタン
![]()