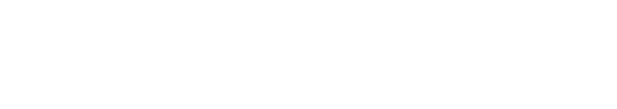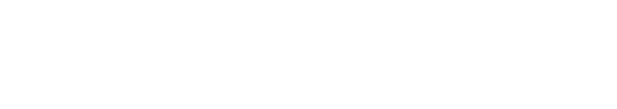すっかり秋も深まり、肌寒い季節になりましたね。
こんにちは。ほと子です。
年の瀬が近づくにつれ、そろそろ年賀状の準備を始めなきゃ…という人も多いと思います。
しかし今年が喪中という方は、お正月をどう過ごそうか迷っているのではないでしょうか?ほと子も初めての喪中のときは、どんなことをしてはいけないのかわからず、不安だったことを覚えています。
今回は、そんな喪中のマナーや、やってもいいこと・避けるべきことをいくつかご紹介しようと思います。
喪中とは?

喪中とは、身内が亡くなった際に故人を偲び、一定期間お祝いごとを控えるなど、慎ましく過ごす習慣のことをいいます。日本独自の風習で、亡くなった方を悼む気持ちを表すものです。一般的に故人が近親者の場合、喪中の期間は約1年となります。友人や知人が亡くなった場合は、期間を短くすることも多いようです。喪中の期間は故人との関係性や地域、文化によって異なります。
また、「喪に服す」という言葉を一度は耳にしたことがありますよね。「喪」という字には、「一定期間喪服を着て、故人の冥福を祈りながら、遊びやお祝い、さらには酒や肉を控えて慎ましく過ごす」という意味が込められています。昔はこのように、喪中には生活自体を変えることが一般的でした。明治時代に出された太政官布告という法律では、喪中の期間が定められていました。父母や夫が亡くなった場合は13ヶ月、妻や息子、兄弟の場合は90日、父方の祖父母の場合は150日など、細かく決められていたといいます。昭和初期に太政官布告が廃止され、現代ではお祝いごとを控える程度となっています。
日本における喪の習慣は、宗教や地域によってもさまざまです。たとえば、仏教では死者の魂を弔(とむら)う儀式が重視される一方、神道では神様への敬意を大切にした行動が求められます。こうした喪の過ごし方やマナーは日本独自の文化であり、他国とは異なる特色を持っています。
喪中にやってはいけないこと

喪中の期間には、故人を偲び、慎ましい生活を送ることがマナーです。特に、神社での参拝や新年のお祝い、結婚式への参加や開催などは、控えたほうがいいとされています。ここでは、それぞれの具体的な注意点について詳しくご紹介します。
神社での参拝
神社は観光地としても人気があり、旅行や普段の散歩のついでに参拝することもあると思います。しかし喪中の場合、神社を訪れる際には配慮が必要です。日本の神道において「死」は穢れ(けがれ)であり、生の力が消えた「気枯れ」の状態であるとされています。そのため、穢れの状態で神社を訪れることは遠慮するようにという教えがあるのです。
どうしても参拝する必要がある場合は、喪服や落ち着いた色合いの服装を選びましょう。また、大規模な神社や、結婚式や七五三などお祝いの行事が行われているタイミングは避けるのが望ましいです。
心を落ち着かせるために日常的に神社を参拝している方は、仏教の寺院でのお祈りやお墓参りをするといいでしょう。故人を偲びながら静かに過ごすことができ、心の整理にも役立ちます。
お正月のお祝い
喪中のお正月は特に気を付ける必要があり、伝統的な祝いごとを控えるようにします。神社への参拝は祝いごとの一環と見なされ、喪中にはふさわしくないとされています。そのため喪中のあいだは、神社への初詣を避けるのが一般的。代わりに、仏教の寺院にお参りをすることができます。故人を偲んで、静かに新年の挨拶をしましょう。
また、門松やしめ飾りなどのお正月飾りも、喪中のあいだは避けましょう。これらの飾りは新年を祝う意味を込めて飾るものなので、喪中の家庭では「祝い」を表現しないほうがいいとされています。その代わり、家のなかを綺麗に整え、静かな雰囲気を大切にするといいでしょう。豪華なおせち料理や鏡餅などの伝統的なお祝い食も、喪中のときは控えます。
喪中のお正月には、家族や親戚で集まっても静かに過ごし、故人を偲ぶ時間にする方が多いようです。ほと子も、喪中のときは豪華な食事は用意せず、親族で集まって故人との思い出話に浸ったことがあります。
また、年賀状は自粛し、年が明けてから寒中見舞いを出すといいでしょう。挨拶状を出すことで、相手に新年の挨拶が遅れた理由を伝えることができます。
結婚式の開催・出席
喪中の期間、基本的に結婚式は避けたほうがいいでしょう。自身の結婚式を予定している場合、日程を見直し、延期することが一般的です。もし結婚式の招待を受けた場合、親しい友人や親族の式であれば、事前に喪中であることを伝え、出席を慎重に検討するのもひとつの方法です。
意外にOKなことも~喪中にやってもいいこと~

喪中だからといって、すべての行動が制限されるわけではありません。たとえば、仏教では死を穢れとする考え方がないため、寺院への初詣はOKです。仏教の教えでは、死後の世界に対する祈りや供養が重要視されるので、喪中には寺院への参拝をすすめられることもあります。
また、お中元やお歳暮も避ける必要はありません。お中元やお歳暮は、日頃の感謝の気持ちを伝えたり健康への願いを込めたりなど、季節の挨拶を兼ねた贈り物の習慣です。喪中でも心を込めた贈り物をすることは問題ありません。しかし贈る相手が喪中の場合には、贈り物の品やタイミングに配慮が必要です。忌中という四十九日の法要が終わるまでは避けたほうがいいでしょう。
また、こちらが喪中である場合でも、出産祝いを贈ることは問題ありません。
ただし相手が喪中の場合は、四十九日を過ぎてから贈る、のしは付けないなどの配慮が必要です。
まとめ
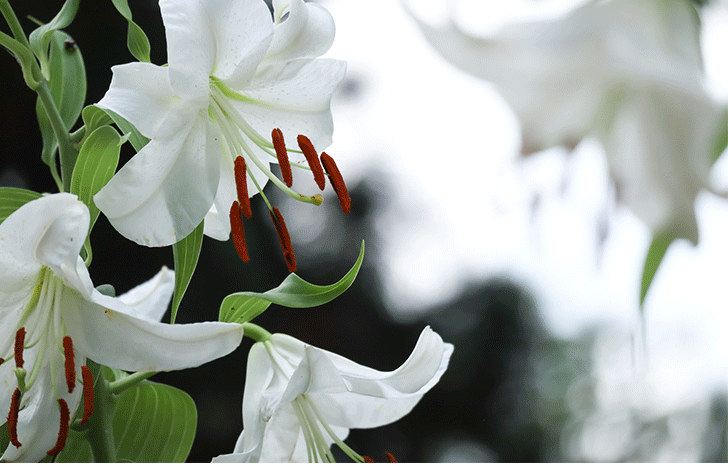
喪中には、控えたほうがよいこともあれば、意外にもOKという行動もあることがわかったと思います。喪中のマナーをしっかりと理解し、周囲の人々への配慮を忘れないことが大切です。喪中の期間は、故人を偲びながら心の整理を行なう大切な時間でもあります。今年喪中の方は、お正月の過ごし方などを参考にしてくださいね。
参照URL
https://www.tokyohakuzen.co.jp/media/530
https://e-mono.jr-central.co.jp/column/ochugen/mochu.html
https://mitsuwa-sougi.co.jp/knowledge/mourn/
秋の長夜に、こんな読み物はいかがです
ほと子’s choice
めっきり寒くなったので、今回はお一人様用温めグッズをご紹介します!
アイリスオーヤマ フットウォーマー 40×40cm 2段階温度調節
税込
![]()
アピックス(APIX INTL) 360°セラミックヒーター 「どこでもこたつ」
税込
![]()
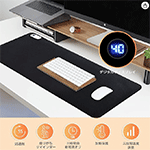

[Tetote] 遠赤 足首ウォーマー 【 カイロポケット付 】 レディース メンズ
税込
![]()